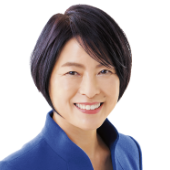文教常任委員会での意見発表
今定例会では比較的委員会の持ち時間が長い方ではありますが、自民党が丸々一日以上かけて通算8時間ほど質疑をしているのに私に与えられた時間は37分程度。
議会の中の議席の少なさに哀しくなる瞬間です。それでも取り上げるべき優先度重要度を考え、質問を削ったり足したり、けっこう頭を使います。それでも満足した質問はなかなかできません。研鑽の日々です。そんなわけで詳細は奈々子reportに書くつもりなので、まずはさらっと復習するような意見発表の原稿をほぼほぼこれが議事録に残ることになるものをご紹介します。質疑の中で明らかにした実態や数字は後日ニュースで。
当委員会に付託されました諸議案、所管事項等について意見要望を申し上げます。
●初めに教師不足についてです。毎年、定数の1割近くを臨任や非常勤で補う採用の在り方は、年度当初から本県所管域で100人を超える教師不足を招いています。これは教員の働き方、児童生徒の学習の質ともに悪化させる要因となっています。年度末に近くなるにつれて、不足が広がり、最長一年間も空白が解消されない事態は本当に由々しきものです。
特別支援学校に関しては教師不足はそのまま安全や命を脅かすことにつながります。教育に臨時はありません。教員の質を担保するために狭き門にすることなどという説明がされることもかつてありましたが、結局採用試験に合格できなかった方々に担任などの要職を任せている例も散見されます。この方々の人生設計をも狂わせていると言わざるを得ません。教員採用試験の門戸を広げ、定数はすべて正規教員とするべく採用を見直すべきです。そのことは教員の多忙化解消、ストレス軽減、いじめや暴力など問題行動の抑止、学習の質の向上などにつながります。正規教員配置率全国平均以下という実態を解消されるよう強く求めます。

●次に部活動の地域移行についてです。地域移行自体は教員の過密労働改善のために検討されるべきとは思いますが、当事者の意向確認が大切です。神奈川県の方針策定にあたり、保護者や生徒に意見を聴取することを求めたことは重要です。
しかし、仮に、地域移行の形が地域クラブでの活動に移る際は、もはや学校教育の一環では無くなり、就学援助の対象からも外れてしまうとのことです。この辺りの事情を方針案市町村にしっかりと盛り込み、かつ経済的事情で部活から排除される生徒が生じないよう、国にも財政支援を求めつつ、県として支援を検討されるよう要望します。
●次に川崎市の小学校のプールの流水事故を受けた本県の対応についてです。
川崎の市議会での質疑などを通じ、プールの注水に関し、学校にあるべきマニュアルが当該校に20年近く前から失われており、口伝えで操作が知らされるのみだったことなど、市としてのガバナンスが問われる事態でした。ミスとすらいえないような軽微な誤りを理由に個人に重い責任を背負わせたこの事件は、こんなことがまかり通るようでは教員のなり手がいっそう減る、という指摘もいろいろな場面でなされました。
川崎のプールを使っている市立の学校の実に4分の1でマニュアルが失われていたということを受けて本県も調査をすべきと求めていましたが、調査をかけ、その結果プールを稼働しているすべての学校においてマニュアルが存在し、研修も行われていると確認できたといいますが、本来こういう事件事故は県行政での不備を点検する機会とするべきだと指摘しておきます。
また、本案件は、被害総額の4分の1に当たる約95万円を、川崎市自身も重過失ではないと認めているにもかかわらず、一教員が賠償責任を求められたものです。本件は、弁護士団体や労働組合などから決定に対して批判的な声明や、処分撤回を求める1万数千件のネット署名が寄せられ、市にも数百件の抗議電話が殺到するなど大きな物議を醸しました。国家賠償法ではなく民法を適用する判断にも疑問が呈されました。香川県三豊市では類似の事故があった際に分限懲戒審査委員会という機関で幅広に討議し、賠償を求めないことを決めています。私はこの判断の是非を論じるつもりはありませんが、本来この集団で検討をする機関は様々な自治体に設置されており、その背景には訴訟リスクを回避するという目的もあります。顧問弁護士の判断のみによらず、場合によっては複数の専門家の意見を聴取できる合議体を設置することが、適正な判断に資すると考えますのでご一考願います。
●次に感染症対策です。学校における感染症対策です。新型コロナウイルスが感染法上の5類に位置付けられて以来、世の中はすっかりコロナが終わったかのような雰囲気に覆われていますが、先月はコロナの第8波のピークを超える新規感染者数がありました。深刻な後遺症のコロナによる学級閉鎖も微増しているということですので、換気や手洗いなど基本的な感染対策を学校に促していただきたいと思います。
●次に中学校の給食についてです。本県でも給食を実施していない自治体は全33市町村のうち2市3町を残すのみとなりました。そして、神奈川県がまだです。県立の中高一貫校において、中学校の給食が実施できていません。学校給食法ではその第四条で義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。としています。育ち盛りの子どもに栄養満点の給食を用意することは自治体の責務です。実施について校長へアンケートをとったこと自体は評価しますが、その結果あまり前向きな回答が見られず、実施のハードルも高いからと手をこまねいていることは許されません。中学校給食を推進するため、当事者主流化の本県の方針にのっとり、保護者や中学生にもアンケートを実施することを要望します。
●また、全国では小中学校の給食の無償化が広がっています。憲法第26条にある「義務教育はこれを無償とする」この精神にのっとるならば、貴重な食育の場である給食を無償にすることは、重要です。格差が広がる中で、経済的に厳しい家庭の子でも食費の心配なく栄養が取れるわけで税金を使って行う施策として実に相応しいものがあります。本県ですでに実施している特別支援学校の給食を無償にするには3億5千万円ほどでできるということです。当事者目線の障害福祉推進条例を制定した本県です。この社会はまだまだ障がい当事者が生きていくには楽な社会ではありません。特別支援学校の給食を無償にすること温かい記憶となって児童生徒たちの中に刻まれ、大きな励みになると思います。条例の本気度を示すべきではないでしょうか。
以上、意見要望を申し上げて当委員会に付託されたすべての議案に賛成して意見要望を終わります。
議案は、次のものです。