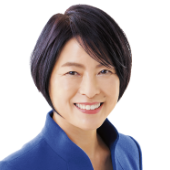代表質問一問一答 土砂条例の見直しと、気候変動を加味した諸基準の見直しについて
(3)土砂条例の見直しと、気候変動を加味した諸基準の見直しについて
[大山議員]次に、土砂条例の見直しと、気候変動を加味した諸基準の見直しについてです。
近年、従来の想定を超えた集中豪雨が相次ぎ、全国各地で豪雨災害が発生しています。被害に遭われた方々に、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。
7月3日に静岡県熱海市伊豆山地区で発生した大規模土石流による土砂災害により、131棟の建物が被害を受け、9月9日の時点で死者26名、行方不明者1名となっており、甚大な人的被害が発生しています。「熱海市盛り土流出事故被害者の会」の方々は、ご遺族含め60人の原告団で元土地所有者を殺人容疑で刑事告訴しました。
静岡県の難波副知事は記者会見で、土石流の起点周辺にあった盛り土について、「違法な盛り土が災害の原因」との見解を示しました。また、別な報道では、被害を引き起こした盛り土は市街地の真上に違法に造成されたもので、行政がそれを止めることができなかったことから、背景に県や市の危機意識の薄さと条例による規制の限界、さらに自治体まかせにしてきた国の不作為という構造的な問題が指摘されています。
関東地方知事会や全国知事会が、土砂等は県域を越えて流通している上、条例で定めることのできる罰則では、不適正な事案に対する十分な抑止力となっていないとして、国に土砂等の適正管理のための法整備を求めていることは重要です。
私たちは、法整備を待たず、隣県の災害に学び、県として災害対策を強化する必要があると考えます。本県には土砂条例があります。静岡の土砂条例よりは厳しい基準となっていますが、まだ次のような課題があると考えます。建設残土を排出する業者や運搬する業者の責務や県の責務が明確ではないこと、土砂搬入禁止区域が限定的であることです。
そもそも、熱海市の現場は土石流危険渓流に指定され、下流の住宅地は土砂災害警戒区域に指定されて、避難などの対策を進めている地域でした。土砂災害警戒区域の上流に大量の土砂を捨てて盛り土にすることを認めること自体、災害を警戒する観点とは矛盾を来しています。
また、昨年わが党の一般質問で、相模原市緑区の山間に谷埋め盛土を行う津久井農場計画について、近年の降雨の激甚化にかんがみ、林地開発許可における降雨強度を現行の10年に一度の数値では不十分だとして、林地開発基準の見直しを求めましたが、答弁は、国基準を準用している、それは適正と判断しているというものでした。
このような姿勢で県民のいのちに責任が持てるでしょうか。熱海の災害をみて、津久井農場計画地の下流域、土砂災害特別警戒区域の愛川町のみなさんの中から、不安の声があがっています。
例えば、川の話に例をとると、流域治水で先進的だとされる滋賀県が2014年に制定した流域治水推進条例では、200年に一度の降雨による浸水想定区域を採用しています。自治体が本気で住民を守ろうとする厳格な姿勢の表れです。
本年、国の流域治水関連法が制定されましたが、そこでは数十年に一度レベルの降雨を想定して基準を決めています。国土交通省は20世紀末比で「気候変動の影響により、21世紀末には全国平均で降雨量1.1倍、洪水発生頻度2倍に上る」と試算しており、これを背景として成立したとのことです。
そこで知事に伺います。
県の土砂条例について、発注者や事業者、県の責務を明記すること、土砂災害警戒区域の上流域や周辺等に土砂を持ち込んで処分することを禁止するなど、条例の中に規定する規制強化が必要であると考えますが、見解を伺います。
さらに、昨今、気候変動の影響により、豪雨が多発している実態を反映し、土砂条例はじめ林地開発許可基準など、本県の災害防止を目的に制定されている制度に関し、基準となる降雨強度の数値を強化し、上位法があるものに関しては降雨強度の数値の見直しを国に進言すべきと考えますが、見解を伺います。
[黒岩知事]次に、土砂条例の見直しと気候変動を加味した諸基準の見直しについてです。まず、土砂条例の規制の強化についてですが、条例にはすでに盛土造成事業者等の義務や県の許可基準等を具体的に規定していますので、新たに事業者等の責務を規定する必要はないと考えています。
また、現在のところ土砂災害警戒区域の上流域における盛土を一律に禁止する考えはありませんが、近県での規制の動向を見定め、必要があれば規制内容の見直しを検討します。
次に、降雨強度の数値の見直しについてですが、降雨強度は国の基準を準用したり、接続する下流側の水路管理者との協議により決定されることから、県が一律に数値を見直すことは困難です。
また、国ではすでに降雨量の増加等を計画に反映させる動きが始まっており、改めて降雨強度の見直しを進言する必要はないと考えています。答えは以上です。
≪要望≫
[大山議員]土砂条例の見直しは、近隣県などを注視していくとのご答弁でしたが、近年想定を超える降雨があるという状態が毎年発生している以上、10年前に基準が改定された条例の想定では、対応できないことは明らかです。注視している間にまた激甚豪雨があったら、行政責任が問われます。
また、土砂災害警戒区域の上流への搬入を禁じることはしないとの答弁でしたが、一律にとは私も求めておりませんので、非常に危険な地域の上、検討することをしていただきたいと思います。
事業所の財産権を尊重する一方で、下流域の県民の暮らしやいのちが脅かされることが止むなしという状況では困ります。憲法29条第2項、財産権の内容は、公共の福祉に適合するように法律でこれを定めるとされています。危険なところに残土を搬入させない禁止区域を土砂条例に位置づけるべきという我々の主張は、まさに公共の福祉の観点を盛り込むことを求める提案です。
一律にとは申し上げませんので、禁止区域の制定とともに、ぜひ早急に気候変動を計算に入れた厳格な条例へと改正することを要望します。