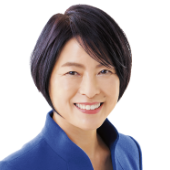文教常任委員会 生理用品、働くルール、学校再編、オンライン、学校PCR検査等
10月4日には私の発言順が回ってきて質問をいくつかしました。
ご紹介するために、委員会最終日に意見発表(委員長副委員長の決定で議案がない場合は省略されることも)の予定の発言原稿を張ります。議事録ができるのは3カ月近くかかるのです(泣)
20211011 文教常任委員会意見発表
・はじめに生理用品の配布についてです。全県立学校女子トイレへの配布をご決断いただいたのは、学校が安心な居場所であるための重要な決断であったと評価します。県内6つの基礎自治体においても設置がはじまっているとのことですが、初潮を迎えたばかりで周期が不安定で失敗することも多い、小中学生にこそ支援が必要です。教育長を先頭にぜひとも県内自治体すべてで実施されるよう要望します。※これは教育長も参加する会議で周知を図ると答弁がありました。「今年度、文教常任委員会唯一の女性委員として強く要望します。」と付け加えました。( ´∀` )
・次に、高校生のアルバイトでよくあるトラブルQ&Aから労働法知識や対処方法などを解説した雇用労政課作成のパンフレット「働く時のルール」についてです。すべての高校に毎年夏休み前に配っていただいていましたが、労働法規を知らないために子どもたちが不当な扱いを受けないよう私たちも作成と配布を求めておりました。高校の現場でも歓迎されているとのことでした。昨年配布されなかったことは非常に残念ですが、今年度は作成されたということですので、授業や講師を招いた講演会などを通じ有効活用されるよう学校に働きかけてくださるよう要望します。
※これは学校へ通知すると答弁がありました。

・次に学校の新型コロナウイルス対策についてです。児童生徒学校関係者に陽性者が出た場合の検査や欠席要請の範囲など基本的な方針すら知らされていないことが保護者の間に不安を呼んでいます。HPに乗っているというだけでは不親切です。保護者間の情報は学校の校区を越えて広がるので、陽性者が出た学校だけに限らず、学校における新型コロナウイルス対応の基本的な対応指針が必要です。例外があったにせよ、どういう例外がありえるのかなど基本的な流れを紙ベース、または家庭へのメール配信でお知らせし、透明性を確保する姿勢こそが安心につながると考えます。新規感染者が低減している今こそコロナ対応にかかる保護者への情報発信を要望します。
※これは必要を感じない旨の答弁で、問題が残ります。
・学校で感染が疑われた場合の検査体制についてです。政府の新型コロナウイルス感染対策の基本的対処方針において「陽性者発見時には幅広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ迅速かつ機動的にPCR 検査等を行政検査として実施する」とされています。、沖縄県では5 月に学校PCR 支援チームを設置しています。保健所と学校が連携して感染拡大防止と早期教育活動再開に資する仕組みとして注目されています。デルタ株に置き換わり、若年層への感染割合が高まる今、学校PCR支援チームのような仕組みを構築する必要を感じます。現在沖縄では教員の負担軽減からこの検査支援チームの民間委託も検討されているとのことですが、今新規感染者数が少ない時こそ第6波に備えた検査体制つくりを健康医療局と連携して検討するよう求めます
※これはこの体制構築の必要は感じないが健康医療局と連携をはかるという趣旨の答弁でしたが、健康医療局に迫った石田議員の一般質問でも上野議員の厚生常任でも受け止めはよくなかったのです。残念です。
・次に県立高校改革についてです。
①私たちは高校改革が始まるころから、統廃合は行うべきではないと、指摘してきました。2016年当初想定した時と比べ、公立中学校卒業予定者数の減少は緩やかです。そもそも少子化というが将来推計は15年先までしか見越していません。
統廃合が行われた結果1学年は平均約7クラス。最大10クラス規模にもなっています。
また、京都府教育委員会の資料によると、全国的には1学年のクラス数はほぼ6~8学級の間が多く、少子化が進行している県ではそれより少ない学級数もあります。本県の1学年9学級や10学級というのは今の時代、突出して多い数です。突出して生徒が学校に詰め込まれているということです。本県の県立高校改革実施計画には、学校規模の適正化について6から8学級以上とすることを基本と書いている。適正と考える理想はきちんと上限を示すべきです。この以上という表現は本当に教育環境を適正にすべきという姿勢が見えません。
また昨年12月には逗子高校、逗葉高校について再編統合を見直すよう請願が出されている。
請願に示された広さや災害時の危険性などの疑念に県はきちんと答え切れていないと考える。本当に合理的な判断がなされたというのなら、地域協議会のようなものを設置するべきです。高校は小中学校ほど地域と密接ではないという答弁があったが、それは地域のコミュニティの核たる学校という存在の理解があまりにも浅いといわねばなりません。現に研究実践校の中にはコミュニティスクールも対象になっている。県教委の中で論理矛盾を来しています。地域の宝である学校をなくそうとするのなら双方の地域の声を丁寧に聞く場を設けることを要望します。
国においては小学校段階での一クラス35人の少人数学級が推進されることとなりました。戦後の教育史を見ても、小学校段階で始まった少人数学級はやがて中学校高校へと波及します。県立高校改革実施計画は20から30校を削減するものであったが、適正な学級数の再検討や人口減少の鈍化や少人数学級の進展、を考慮に入れて再検討すべきことを指摘します。米百俵の逸話を引くまでもなく、本県が子どもたちの学びを保障するために県立高校百校計画をもって整備してきたその思想が経済効率優先でないがしろにされている、そのことに大変な危惧を持っています。
また、統廃合後の跡地活用について1期目に統廃合した非活用校の跡地は4校中3校が民間売却されたと答弁がありました。学校の校地の中には県民が学校になるならと寄贈した土地も多いと聞いています。特別支援学校の設置基準が定められた今、特別支援学校の教室不足数が全国二位の本県ですから、特別支援学校として転用する可能性を含み、慎重に判断することを求めます。
※県立高校改革における学校削減は規定路線ですが、少しでも抑えられるよう頑張らなければと思っています。
・次にオンライン学習についてです。国が端末の更新費用の方針を示さないままに進めている事業ですが費用負担を隠したまま実施することは無責任ですので、国に強く費用負担を求め、保護者負担を求めるべきではありません。また、現在高校生の7から8割がスマートフォンで授業を受けているといいますが、一人一台端末を公費負担で行うべきです。本県では新しい文房具という位置付けて保護者負担を求めるといいますが、デジタル教科書の導入も図られることから、教科書無償の精神で、高校段階での教科書は有償だとしても、都道府県の中では公費負担にしているところが15あるということです。本県も子どもの教育の機会均等の精神で一人一台のタブレットを国費か県費でまかなうよう要望します。
また、オンライン学習を支援するICT支援員は障害者雇用の推進の観点からも4校に1人ではなく全校配置を目指すよう求めます。
※答弁は財政負担に関しては後ろ向きです。
オンライン学習を行ってほしいのにやってくれないという声があります。あくまでも授業を補完する形で、必要な時にはオンライン授業は行われるべきと考えますが、実施できない場合の課題など学校から丁寧に聞き取り支援する仕組みを作るよう求めます。
※そういうルートはあるとのことですが…
次に、わが会派の一般質問でも取り上げたように、電磁波の影響を懸念する子どもたちに対して教育長はご答弁の中で「また、電磁過敏症に限らず、健康面に不安を抱える子供がいれば、これまでもその状況に応じた対応を図っています。今後も、国の示す基準などを踏まえながら、健康面への影響に対する情報の収集に努め、子供たちの安全性を確保してまいります。」とお答えになりました。
しかし実際には、影響が気になるなら遅刻して来いというような対応がなされる自治体に住む県民からの声を聴いています。県教委が丁寧に対応を想定していてもそれが現場の教員や学校に伝わらなくては意味がありません。電磁波の影響を不安視する保護者や子どもたちに具体的に寄り添い対応することを求めます。
※これも実際冷たい対応が行われる例を聞いていますので、現場の課題を共有できるかともに解決する姿勢が求められます。