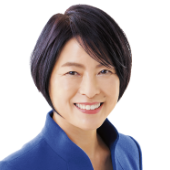自治体学校 国のデジタル化戦略とICT教育を学ぶ
県議団の井坂団長は行財政に強い。市議経験も豊かな人であるからと思いつつ、「そもそもどこで学んだの?」というと「自治体学校」と即答。ほかにも多くの議員が自治体学校の意義深さを語りますので私も極力参加しています。11月7日に横浜市健康福祉総合センターで開かれました。
自治労連・地方自治問題研究機構主任研究員の久保貴裕氏による国のデジタル化戦略は想定を超えた問題をはらんでいました。また、長々書きそうなので要点を絞ります。あ、でも冒頭、私も最近読んでいる堤未果氏の「デジタルファシズム」を紹介されていました。これは本当に中国やアメリカに日本の個人情報を譲り渡す怖さが記されていて恐ろしい本です。でも彼女のすごいところは必ず希望が見えるところ。GIGAスクールの問題に気づいて自ら行動した高校生たちの話など。あ、やはり脱線(笑)
・デジタルの技術は未熟であり、セキュリティも万全ではない。誤った使い方をすれば住民に重大な被害、権利侵害をもたらす。
・デジタル庁は初の内閣直属の常設組織。強力な権限を与える。職員600人中200人は民間企業(主にIT産業)から登用
・自治体版デジタル庁は首長と、CIO(最高情報責任者)、CIO補佐官が当たり民間企業方積極的に人材登用。財政誘導もされる。守秘義務や含む専念義務など公務員の服務規程の適用なし。所属する企業の入札参加も制限なし!!登用は自治体の判断による。(CIOは副市長が望ましいとされているのに神奈川県は補佐官もつけず、いち早くLINE社の執行役員をCIOとして起用。CIOに民間企業からの登用は総務省自体が想定外)
・デジタル改革関連法において自治体の個人情報保護条例を改悪。国が統一ルールを定め、地方の情報の取り扱いを国が設置する個人情報保護委員会に一元化
などなど一体の独自の行政サービスが阻害される怖い戦略と、それに対して対面の窓口業務でこそできる細やかな行政サービスの例が語られました。
もっと書きたいのですが、決算とコロナ特別準備の集中する週なので余裕がありません。久保氏の「デジタル化でどうなる暮らしと地方自治」(自治体研究者所収)をお読みください。
午後の分科会ではICT教育の分科会。教育現場の先生がデジタル端末を使った教材の功罪について子どもたちのアンケートに基づき報告、納得でした。

結論、魅力的な分科会も盛りだくさん、熱海の土砂災害の被害者の方の報告もあり、横浜市長選の報告もあり、本当に参加してよかったと思えました。自治体問題研究所さんありがとうございました。
・
・