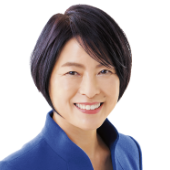文教常任委 一人一台PC インクルーシブ教育 医療的ケア体制
12月に開かれた文教常任委員会では、国で定めた特別支援学校の設置指針の最終素案修正版が示されました。これの評価や3議案(高校施設整備・高校奨学金貸付・教職員給与等)への姿勢が問われます。しかし質問時間が短い(´;ω;`)ウゥゥ
私は・高校段階での一人一台パソコンを保護者負担としたことの問題を指摘し公費負担を求めました。中でも生活保護家庭に教育扶助費の対象になっているのかどうかも確認しないで保護者負担を決めたことは大きな問題だとして指摘しました。のちに生活援護課を通じて調べたところこの問題には厚労省からも通知がだされ、全員が購入しなければならないものは 生活保護の教育扶助対象とすることが認められているのでこのことを各地の生活保護を所管する福祉事務所に知らせるとのことでした。
次に、インクルーシブ教育について、推進校数の拡大をめざし、成果ありきのアンケートではなく、謙虚に課題を抽出することを求めました。
最後に医療的ケアに関して。本県は17の特別支援学校に医療的ケアが必要な児童生徒が通いますが、担当は13人。兼務の先生もいます。(千葉県では30校に在籍し、30人の担当医が対応します。)看護師さんや学校医、担当医、がかかわりケアに当たるわけですが、どうもその連携がうまくいっておらず、結局、保護者の力にゆだねられることが多いというお声を障がい者教育関係者から聴いています。しかしその問題を所管課は認識できていないことがヒアリングの中でよくわかりました。現場の声を聞き取る会議が設定されていますが、なかなか問題把握につながっていない歯がゆさがあります。アンケートなど現場の声を聴く仕組みを構築することを求めました。
いかに、最終日の意見発表をご紹介します。

20211214 文教常任委員会 意見発表
共産党県議団を代表し、当委員会に付託された諸議案・所管事項に対し意見要望を申し上げます。
まず、高校段階でのオンライン学習における一人一台端末整備の保護者負担についてです。
そもそも文科省が義務教育段階だけに国庫負担を決めたこと自体に問題があります。同省が公表した直近の数字で、中学卒業生の98.8%以上が高校に進学します。すべての子どもの学びを支える観点に立てば義務教育を理由にした線引きは道理がありません。そういう状況にあっては自治体が国の不備を補完して財政支援をすべきであって、18府県がその立場を選んだことは自治体の役割を果たしていることにほかなりません。
教育局は生活保護世帯の教育扶助費の対象か否かも把握のないままに保護者負担を決めました。現状、生活保護費は数万円の文房具を買う余地などありません。保護を利用していない世帯であっても学費ねん出のためにダブルワークトリプルワークを行い、他の子たちがいく塾に通わせることもできず、修学旅行に行かせられるかどうかドキドキする、そういう思いで子育てをする家庭の思いに寄り添うべきです。子どもの貧困に対する想像力が欠如しているといわざるを得ません。学費が無償になっても学費相当の教育費が必要といわれる中、コロナで疲弊する家計状況もある中で、国策で導入する教具に一度に数万円の負担を課すことの冷たさは再考されるべきです。用意できない家庭には貸し出しが用意されているといっても、用意できない家庭だと知られることの不安に心を寄せていただきたいと思います。たとえば生理用品の配布について、トイレの鏡の前への設置ではほかの子に気兼ねして持っていけないのでトイレの個室の中においてほしいという声すらあるのです。子どもの心の機微に配慮し、いじめの種をつくらないためにも、私学を所管する知事部局とも連携し、公費負担を検討するよう求めます。少なくとも、東京都が補助制度を設けたように、教育の機会均等の精神に立ち返って公費負担を検討されるよう要望します。
次にインクルーシブ教育についてです。
パイロット校から初めての卒業生を送り出すと同時に推進実践校の数を増やすという展開のしかたは、あるべきインクルーシブな学校つくりを目指すうえで、拙速だとは思います。しかし急増する、支援が必要な生徒の学びの場を確保するために、走りながら条件整備を考えていく状況になることもある程度やむを得ないのかとも思います。そうであれば、謙虚にその在り方を顧みる必要があります。東京都で特別支援教育に当たってきた元教員がおっしゃっていた言葉に「障がいのある子が教材になってはいけない」というものがあります。人と人が交流する際にお互いがお手本や反面教師など影響を与え合うのはもちろんですが、その成長がマジョリティの側だけにみられて、障害のある少数の子どもの発達が後回しにされがちな状況を懸念するものです。初めての教育形態を試みて始めて卒業生を送り出す前に問う中身が、目標の到達度を図るものだけであっては県教育委員会のインクルーシブ教育にかける熱意と誠意が疑われます。卒業生や生徒や保護者、教員に対して匿名回答も可能とし、「この学校でどのような課題がありますか」「どういう改善の方法がかんがえられますか」と問うことはすぐに改善が図られなくても、よりよい教育環境を整備する上で不可欠な問いかけです。単に自由記載欄を設けるのみならず、積極的に課題を抽出する誠実かつ謙虚な姿勢を特に子どもたちに示していただきたいと思います。
次に特別支援学校における医療的ケア体制の強化についてです。本年2021年9月に医療的ケア児支援法が施行され、自治体においてもその体制整備が求められています。看護師体制については強化が図られるとのことで期待しています。
一方、看護師と連携して医療的ケアにあたる担当医師の巡回を増やしていただきたいというお声を現場の先生たちから伺っています。個別のマニュアルを作成してケアに当たっておられるということは聞いていますが、そのマニュアルにはコロナ感染症などは含まれていません。感染リスクにおびえながら高い緊張感の中で、ケアに当たる看護師の皆さんの不安に答えられる体制にないことを私たちはうかがっています。医療的ケアの係が入る年4回の会議や、看護師さんが入る年3回の会議が県教委主催で設けておられることはうかがいましたが、これら会議や学校長経由では、現場で支援にあたる教員や看護師の悲鳴が県教委にとどいていないことが勉強会を通じて明らかになりました。担当医は病院での業務が忙しく緊急の連絡がつながらないため、保護者に連絡、対応してもらっているのが実情で、それが難しいときは、救急車を呼ぶしかありません。これが、担当医に連絡がいかない本当の理由だとのことです。現在、医療的ケア児のご家庭でも共働き家庭が増えて、職場への連絡は困るという例もあるといいます。
「医療的ケア児支援法」第10条の2「学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が保護者の付添いがなくても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。」とあり、保護者が学校への付き添いを拒否した場合、現状の担当医制度では、医師の指示もなく、保護者の協力もないでは、看護師が子どもに医行為(医療的ケア)を学校で行うことが不可能になってしまいます。だから、担当医の来校回数を増やし、少しでも担当医と話す機会を作り、適切な意思疎通ができる体制を整え、保護者がいなくても学校で医療的ケアが安全に実施できるようにする必要があるのです。「医療的ケア児支援法」の法の精神に則り、保護者の付き添いなしで医療的ケア児を受け入れるのであれば、担当医だけではなく、学校で医療が提供できる人的・物的・組織的な体制作り、設備の改修等、必要なことは山のようにあるとのことです。各学校任せでは片付かない事態に陥っていることをぜひ把握していただきたいと思います。
高度な医療を必要とする生徒・児童が通いながら、保護者に医療のおおくをお願いするしかない実態は放置できません。担当医の増員、巡回回数を増やすことなど、法の精神にのっとった体制整備、そして現場の声を届けやすい仕組みの構築や聞き取る姿勢を示していくことを要望します。
次にかながわ特別支援教育推進指針についてです。横浜川崎に新たな特別支援学校整備さらに藤沢に増改築の方針が示されたことは歓迎いたしますが、具体性をもって整備計画を立てることを求めます。また、分教室は適正配置としるされていますが、設置当初は5年間で解消すべき形態として整備されたことを常に念頭におき、一刻も早い解消を位置づけ、現存する分教室にはさらなる施設、人ともに環境整備を行うことを求めます。
次に議案第144号に関してです。高等学校施設整備工事関連費が繰り越し明許となっていますが、この中身は瀬谷高校と瀬谷西高校の再編統合に伴う工事を含みます。長期的な視野に立って、高校は将来的な少人数学級に対応すべきであり、通学の負担や地域貢献の要素も加味し、小規模校で地域に点在していることが求められます。高校統廃合に反対しますので本議案は反対です。
次に定県第174号議案についてです。本年10月の人事委員会の勧告等を勘案し、職員の給料月額を号級の高い方に対しては国家公務員の水準に合わせて下げる、ただし4年間は現級補償というものです。人事委員会勧告より長い期間現級補償を行うことは評価しますが、代替策として提示されている地域手当はいつ増やされるか明確ではないとのことです。
先の委員会で提示された教職員の期末手当引き下げに反対した際も申し上げましたが、コロナ禍で頑張り続ける教職員の給与をこの先も下げるべきではないと考えますので、174号議案には反対いたします。
また、他会派からも指摘がありました委員会報告資料に関してですが、円滑な審議のためにという当局ご説明がありましたが、これは県民にも公開されるものであるという認識のもと議会から指摘を受けるかもしれない案件こそ審議の対象にすべきと考えます。県行政を県民目線で推進するために適切な報告資料を作成されますよう要望します。
他に付託された定県第163号議案には賛成し、意見発表を終わります。