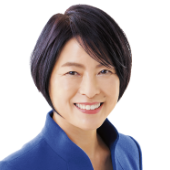急施事件。受検、修学旅行、休校判断など。
緊急性を有する場合に開かれる定例以外の文教常任委員会が開かれました。まん延防止等重点措置が今日から2月21日まで神奈川県に適用されることを受けて、学校活動全般について問うものです。私は以下の四点をうかがいました。
①入学者選抜受検機会の確保:感染によって入学試験の受験を逃した生徒のために追試験の日が設けられているが、
その日をも逃した場合の救済策 A 用意されている 筆記試験など活用して取りこぼしがないよう配慮している。
②修学旅行のキャンセル料の公費負担:県立学校は公費負担としている。しかし市町村立の小中学校は市町村の判断。保護者負担の可能性もある。→A 国の地方創生臨時交付金の活用を紹介し、他市の状況も伝える
保護者に負担義務があるはずもない話ですから公費でまかなわれるべきです。
③休校や情報発信など県教委としてのガイドラインの設定:これは昨年来求めてきました。
(自民党からも,
市町村によって判断がわかれ、国や県の何らかの指針が欲しいという旨の新聞報道が紹介されました。→A 昨年8月の文科省のガイドラインに沿っている。新たなものを求めても出てこない。地域の実情に合わせて市町村教委が判断すべきという当局答弁に、地域の実情というより、オミクロン株の実情に合わせるべきではないか。)
私からは「専門的知識がないため、万全を期す必要がある」という、一人の感染で全校休校にしている自治体のコメントを紹介。学校に医療の専門知識がないことはもっともだが、この状況は感染抑止をもとめるあまり学習権が侵害されている状況にある。特別支援学校の先生から、一人感染で修学旅行がなくなり、一人感染で文化祭もなくなり、これでは子どもたちはどこで学ぶ楽しみを得るのかという声もあった。専門的知見を有する医療部局が県にはあるのだから、連携して最低限の基準を県教委がつくるべき。
神奈川県の教育現場をしっているのは文科省ではなくて神奈川県教育委員会では?学校に配布されている抗原検査キットもあまり活用されていないという状況が先行会派の質疑の中であきらかになった。保健所をまつのではなく保健所業務を軽減するためにも、抗原検査キットを活用していいのかどうか、濃厚接触者の定義をどう生かすのか。何割の感染者で休校の判断をするのかなど、専門的知見を持つ部局と連携してガイドラインをつくるようお願いしたい。
④学校での白濁パーテーションの交換を:横須賀の小学校で音楽や給食の時間にパーテーションを設置しているが、それが長い間使ってきて白濁しているという声があった。写真も見た(当局にも提供した)あれでは前が見えない。
そもそもパーテーション設置はもとめられているのか→A 特に求めていない
学校の中には適切に新しいものに交換したところもある。白濁したものは交換するよう自治体に伝えてほしい
→A 伝える。
最後に、議会に提供する資料について。今までは児童生徒の感染者数とともに重症者数が示されていて、子どもたちは重症化はしていないんだなとか判断することができた。聞くところによると、文科省が煩雑さを避けて報告を求めていないのだということだが、従来と違う資料になるならその旨をお知らせ願いたい。
感染抑止と学習権の保障は両立が難しい課題ではあるが、今の状況は学習権が侵害されている面が強くなっているのではないか。ガイドラインの作成を再度お願いして質問を終える。