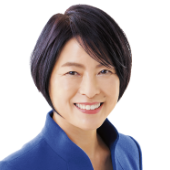一般質問 安全なファミリー・サポート・センター事業について
9月16日の一般質問です。取り上げるかどうか自体、議論になった案件です。厚労省にいってヒアリングもしました。
(2)安全なファミリー・サポート・センター事業について
続いて、安全なファミリー・サポート・センター事業についてです。
ファミリー・サポート・センター事業は、国が推進する市町村の事業です。子育てを地域で相互援助する組織と説明されています。センター運営の費用負担を含め、国、県、市が同率の補助を行っています。民間でいえばベビーシッター。保育園の送迎や美容院に行く間の見守りなど、利用者の就労の有無を問わず、気軽に安く子どもを預けられるということで子育て世代には需要はあるものの、専門性は問われていません。
県内では30自治体がセンターを設置し、資格の問われないアドバイザーが仲介や紹介を行っています。サービスを利用する依頼会員・提供会員・両方を兼ねる会員の合計56,245名が、この事業を利用しています。多様なニーズに応えるというと聞こえはよいのですが、本来なら専門性を持った保育士が担うべき保育の事業を、無資格の人でも担えるところに問題があります。

公の事業である以上は、最低でも安全性の確保が必要です。2010年、大阪の八尾市でファミサポに預けられていた子が心肺停止で発見された事故では、その解決を行政側が当事者任せにしたことが国会でも議論され、2017年11月に児童福祉法の施行規則が改正され、登録時に救命救急などの安全講習研修が義務付けられました。これとは別に、24時間程度の任意の研修もあります。
しかし、本県ではこれらの研修を、法改正以前はもちろん、改正後にもコロナ禍などもあって実施されていないケースもあるとのことです。こういう状態では、安全性にはなはだ疑問があると言わざるを得ません。
また、事故が発生した際の対応規範は、「市町村は発生を早期に把握して援助を行い、必要な措置を講ずること」という通知に過ぎません。全国でこの5年間に重大事故として報告されただけで、本県の1件含め7件の骨折事故が起きています。解決に公の責任が問われます。
また、活動報酬についても問題があります。提供会員だった県民からご意見をいただきました。子どもの命を預かる仕事が最低賃金を割り込む水準でよいのか、というものです。報酬は、基本、依頼会員から提供会員へ直接支払う仕組みになっています。県内には、小田原市等のように時給700円という低い水準もあれば、海老名市のように平日は1,000円、土日は1,300円という水準を公費を投入して維持している自治体もあります。海老名市は、お子さんの命を預かることや提供会員の諸経費を考慮しているとのことです。有償ボランティアとはいえ、宿泊を伴うケースもあるといいます。子どもの命を預かる活動に対して、どこまで正当に評価するのかが問われます。
そこで知事に伺います。
保育の専門性がない方が担うファミリー・サポート・センター事業で預けられる子どもの命を守るために、研修を受けていない会員のいる市町村へ研修の徹底を促すべきと考えますが、見解を伺います。
また、重大事故が発生した際は、当事者任せにせず、指導監督権限のある県が解決のために市町村を指導すべきと考えますが、見解を伺います。
さらに、海老名市のように利用者負担の軽減と最低賃金レベルの報酬を保障している自治体を応援するために、報酬も含めて本県も国も財政支援の拡充をすべきと考えますが、見解を伺います。
[黒岩知事]
次に、安全なファミリー・サポート・センター事業についてです。
ファミリー・サポート・センター事業は市町村が子どもを一時的に預けたい保護者と地域のボランティアを繋ぐ取り組みであり、事業実施時の子どもの安全性確保は重要です。このため、市町村はボランティアに対して事故防止などの研修会を定期的に開催しており、未受講者には個別に連絡を取って受講を促しています。
県も機会を捉えて市町村に研修等の受講状況を確認し、必要に応じて受講の徹底を働きかけていきます。
次に、事故発生時の対応ですが、市町村には事故を未然に防止する努力義務が課せられており、県は指導監督者として市町村から事故の発生状況や再発防止の改善策に関する報告を受けることになっています。
そのため、不法行為や過失などが原因で当事者間での解決が求められる場合を除き、市町村の対応が不十分な場合には助言を行っていきます。
最後に、県と国の財政支援の拡充についてですが、ファミリー・サポート・センター事業の経費を見直す場合には、実施主体である市町村の財政負担を生じることから、市町村と意見交換をしてまいります。
≪意見・要望≫
[大山議員]
次に、安全なファミリーサポート事業についてです。
子どもの大切な命を預かる保育という仕事の専門性を軽視した現行制度を、少しでも安全なものとすることは喫緊の課題です。サービス提供会員に対する報酬の改善は、国に働きかける前に市町村と相談するというトーンでしたけども、これ、ぜひ海老名市の姿勢にならって国に働きかけていただきたいと思います。
また、事故発生時に監督権限を行使するという趣旨のご答弁がありまして、それは評価いたします。登録前の研修やフォローアップ研修を徹底することも、指導監督権限のある本県の重要な責務です。県の取り組み次第で守れる命を守ることができる、その重みを踏まえて事業にあたっていただくよう要望いたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
感想:ファミサポで提供会員だった方が、自分はやめたけれど低すぎる報酬が問題、今後のために改善を、という県民の方からご意見と丁寧な資料をいただいたことが取り上げたきっかけでした。しかしこのファミサポをどうみるか。団会議は紛糾しました。本来、公の機関がそういう体制を持つべきという意見と、それでも実際のニーズがあるのだから過渡期としてこの仕組みに頼るのもやむなしでしょう。いや、過渡期という考え方自体が保育の専門性をないがしろにしている…等々。国会でも田村智子議員が、安全性の確保については問うていました。無償化の対象にする問題も。
畑野君枝さんと加藤なを子前県議と国会に行って厚労省にヒアリングしました。党の見解はファミサポを積極的に肯定するものではありませんでした。しかし、事故が起こった場合に、無過失でも補償があるJSC、日本スポーツ振興センターの災害共済制度を田村議員が求めた際、答弁は「御指摘につきましては、災害共済給付制度を所管する文部科学省と認可外保育施設等を所管する厚生労働省を中心にまず検討を行っていくべき課題であると認識をいたしております。」と言っていたのでこれどうなったか聞いたら来年できる子ども家庭庁で検討されるでしょうという話で、ここでも答弁がいい加減な印象を受けました。県ではファミサポ事業者は何らかの保険に加入しているということだったのでここまでは質問しませんでしたが…
これは答弁が後退した例です。事前には報酬について国に意見をいうことになっていたのに、上席から知事に行く段階でまた市町村の判断にゆだねる形に後退。皆さんのご意見を伺いたいと思います。