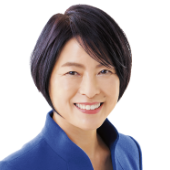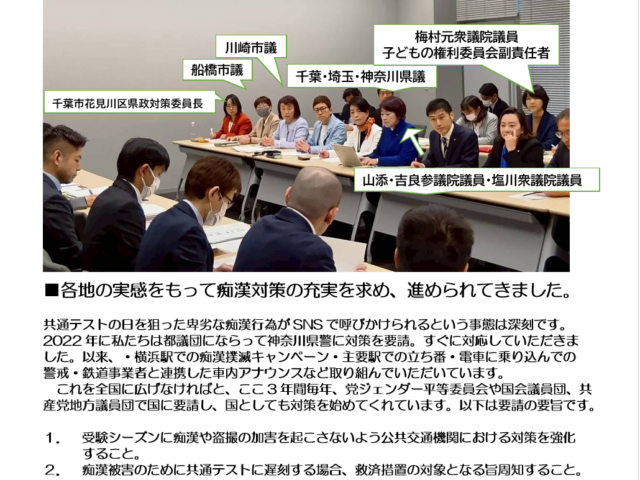自治体学校修了レポート
今日の報告はコンパクトです!だらだら報告した二日分をお読みいただいた方、ありがとうございました。たくさん学んだ岡山自治体学校の修了レポートを書いたので、最終日の様子をふくめ、エッセンスをお伝えできるかと思い、こちらにも張ります。
第65回自治体学校in岡山修了レポート
大山奈々子 日本共産党神奈川県議団 職種 県議
学校への参加 3or4回目
【1日目】
※記念講演感想
中山徹先生 自治体問題研究所理事長 奈良女子大学
異次元の少子化対策が、20年間進めてきた新自由主義的な政策に手を付けず、政府の予算措置の範囲内の対策にとどまっているという指摘が重要だと感じました。
どのような政治勢力が伸びれば新たな政策が実行できるのか、明確に示すこと、社会に不満を持っていたがどうしていいかわからない層が投票に行くことが重要ということを念頭に活動したいと思いました。投票率が上がるのは若者と女性の投票率の上昇がカギになるということで、政策のターゲッティングも見据えながら、しかし個人的には政策から排除されがちな高齢層への配慮も忘れずにいたいと思いました。
岸本聡子先生 東京都杉並区長
ミュニパシリズム(地域主権)をヨーロッパで推進する主体であった先生の著書を読み期待していましたが、期待にたがわぬ講演でした。①運動と、②地方政治と、③地域経済この3要素が重要な中でヨーロッパの各種運動が公共財の自由化を背景にしていること②は自治体で権力をとるために杉並で自らが実践してこられた首長をとること、議員選挙でも市民がさまざまな手法で投票率を上げ、議会でパリテ(男女同数)が実現し、その変革の結果質問の中身ががらりと変わったという成功経験、③は地域経済を活性化するために公共の再生と住民の政治への直接参加がいかに重要か日本の自治体でどんな挑戦ができるか問われている。岸本区長が何度も労働分野の課題を口にしておられ、どのような刷新がはかられるか楽しみだ。
リレートーク
奈義町 森藤政憲議員:合計特殊出生率が2019年に2.95に達して多くの取材を受けている。2007年の花房市長の誕生で「町民の身近なところに目をやる政治」「箱もの建設は抑制する」等の姿勢と、と住民運動の実践、議会のプッシュが力になった
施設一体型小中一貫校の問題で有権者の半数近い署名を集めた話は感動。
非正規公共労働者の挑戦 小川裕子(自治労連非正規公共評議長)
会計年度任用職員制度の矛盾は問題意識が強かったのでそれをリアルに聞けたことは収穫でした。非正規職員の処遇改善の名目で始まったのに、制度は矛盾していて専門的な仕事を行うものが4割、5割以上がやりがいを感じて働いているの年収が200万円未満、これはやりがい搾取と言える。保育士の4割以上が会計年度任用職員だとは。経験と憲さん、知識・スキルの向上が専門性を持つために必要でありそのための安定雇用が課題。長期にわたる事業の外部化で自治体職員の事業理解が欠如しているという指摘は深刻。党同社の団結と住民の理解促進が解決への道、
備前市 中西裕康市議
備前市教育庁が給食費や教材費の無償化の条件としてマイナカードの取得を挙げたことはニュースになったので衝撃を受けていたが、現場の教員に知らされることなく保護者に通知が発出されたと聞いて教育所管局の劣化に唖然としたが、その後子どもたちに平等な教育保育を求める実行委員会がたちあがり、ネット署名やマスコミの活用、法制の学習、国会議員との連携で腫瘍要件の撤回を勝ち取った経緯は市民の持つ力の大きさを実感。
【3日目】
本多滝夫先生 (龍谷大学) 暮らしから考える自治体行政のデジタル化
デジタル田園都市構想の中身が漠然と理解できた。パーソナルデータを蓄積している行政の情報システムと民間事業者の情報システムとの連携基盤を全国に構築しようとしている、先進地域の会津若松スマートシティのデータ連携基盤の持つ情報の多さ(購買履歴、地域農作物需給情報等々)は、身ぐるみ管理される恐怖を感じ、かつそのデジタル社会のパスポートがマインナンバーカードという構造、監視資本主義への道を開きつつある状況がリアルに。
今後求められる対応の提起が短時間で残念だったが、焦眉の課題はマイナカードの市民カード化阻止。行政手続きをマイナポータルからのアクセスに限定させない。複雑な事情をもつ住民対応を単純化断片化してオンラインの対応だけではすませられない。ガバメントクラウドの利用は現時点では任意なので自治体は任意に検討すべし、実地監査や定期検査のデジタル技術化は慎重な検討が必要。データ連携基盤の透明化確保と、自己情報コントロール権の確立が課題
太田昇先生 (真庭市長)
「中央ではなく地方から国を変える」心意気と実践は、私の故郷、尊敬する蜷川知事時代に府庁に入庁され、のちに副知事まで務められたご経歴をうなずかせるものでした。地域資源を生かした「回る経済」確立のための取組でバイオマス産業、生ごみ・し尿液化事業、シェアオフィス、地域コイン等々独創的な取組の数々は背景に人材登用の柔軟性、働きやすい環境づくり、があったことを知りました。(服装など細かいことは決めない等)資料を保存版にしたいお話で、最終日の講義では早退者もいるので惜しいと思われる中身でした。田舎だからできることだとは思わず、都会でも生かせる発想を取り入れたい。
2日目の分科会・講座の感想
講座11
自治体政治・行政入門 柏原誠先生 大坂経済大学 政治学・地方自治
自分としては行政のことを経験的にわかり始めた気でいるため、理論的な支柱が欲しいと思って参加した、その思いに応える素晴らしい中身と「学校」の名にふさわしい授業でした。自治体の目的として、地方自治法「住民の福祉増進を図ることを基本」憲法第15条2項 公務員であり全体の奉仕者である、そして議員も公務員であることの確認。
明治憲法には地方自治がなかったこと、「地方自治は民主主義の最良の学校」政策の実験場であり、防波堤であり、補完機能をもつこと(神奈川県は政権の旗振り実験場の側面が強く、防波堤機能が極めて弱いことを再認識)等々、憲法93条が規定する議事機関であって議決機関ではないということ、片山善博元鳥取知事のいう「八百長・学芸会」減少などの嘆かわしさは思い当たり、議会改革の課題と思えた。議員定数削減を考えさせる共同のワークは久しぶりに生徒の立場になって学んだ。資料は保存版にしたい。
講座12
自治体財政のしくみと課題 K先生 静岡大学
必ず講師にお伝えください。本当に残念な講義でした。周りの方の集中力が途切れているのがよくわかりました。①タイトルに期待されるものが中身と違っていたこと(受講者は自治体の予算や決算にまつわる基本を学びたい思いでしたが、実際は集権的な国の策動が語られました)②資料が雑でした。私は前から3列目、魏標準的な視力ですが、パワーポイントの字が読めない、通し番号もない、説明資料がすべて印刷されてはいないという事前説明もない、今どこを語っているのか追うのに疲れ、あきらめました。③解説なく難解な行政用語の乱発。10年程度地方自治に携わっている私は何とか理解できましたが、新人さんは置いて行かれたようで、実際何もわからなかったという声を聴きました。察するに中身を詰め込みすぎたのではないでしょうか。参加者の反応を見る時間がなかったのかもしれませんが、かなり独善的な講義だという印象が否めません。講義の基本ができていない。大学の先生ということで学生は大丈夫なのか心配になりました。パワポに頼ると自身は出来たような気持になりますが、まずはわかりやすい資料を整えること。ユニークなお話しぶりで、部分部分は傾聴に値したからこそ惜しかった。改善を求めます。参考になったということでは私もパワポを使って報告することがあるのですが、反面教師的に学びました。
討論・運営で気づいた点
大規模イベントの運営お疲れさまでした。古い会館でかつ、オンライン併用は大変だったとお察しします。しかし諸アナウンス含めうまく運営されていて助かりました。改善をお願いしたい点は①資料に講師の勤務先だけではなく何の御専門か明記をお願いします。 ②基本の分厚い資料の中にそれぞれの分科会の場所が一つ一つ載っておらず別紙になっていたのでそこは不便でした。1対1対応でお願いします。
③分科会11,12会場の空調が冷えすぎでした。
全般には大変満足でき、深い学びにつながって議員活動に生かせる中身でした。ありがとうございました。
岡山の街はエスコートゾーンや自転車レーンなど整備されていて、高すぎる建物が少なく、青い空と緑が映える素敵なまちでした。
私も次回開催の神奈川で活動しています。今回の感想・教訓を次回に引き継がれることを期待します。