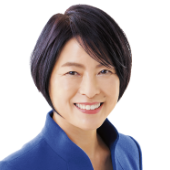過労死等防止対策シンポジウムでの学び
横浜市技能文化会館。毎年11月に厚労省の主催で行われる過労死シンポ、極力学ばせていただいています。冒頭には神奈川県労働局(国の組織)神奈川県の産業労働局の雇用労政課長がご挨拶をされました。

「疲れたら休む、休める、休ませる社会の実現に向けて」という基調講演(久保智英 独立行政法人 労働健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 過労死等防止調査研究センター 上席研究員)」/「過労死遺族より体験談」/「企業の過労死再発防止に向けた取組事例紹介」というような考えさせられる学びの多いシンポジウムでした。過労死ご遺族の声は毎回魂に響きます。今回も中学校教員がなくなった例でした。
神奈川労働局からの現状報告では、年間総労働時間の推移がコロナ禍で低下したが、急増している運輸・郵便業を筆頭にまた増えてきている状況。
過労死等の労災補償状況は2023年までの5年間で脳・心臓疾患、精神障害ともに過去最高となっていることがグラフで示されました。2024年問題と言われる、時間外労働の上限規制が適用猶予されていた業種※に4月から適用されるようになり、それらに対する具体的な取組が紹介されました。(※建設、自動車運転、医師)パワハラの訴えに対応しない本社に対し、労働局に紛争解決援助の申し立てが行われたこと。それに対する援助の実態が示され、考えさせられました。
「疲れたら休む~」の久保先生のご講義では、行政課題を知りたいと思っていましたが、まず、基本的に個人の時間の過ごし方で上手に休む方法を教えていただきました。ユニークで非常にわかりやすいご講義でした。いろいろ数値化できるQRコードもちりばめられていました。心に残ったポイントを。
●日本の有給休暇の取得状況は香港シンガポールカナダフランスドイツイギリスアメリカメキシコオーストラリアニュージーランドの11地域で最低の63%(G7などで比較してもらいたいと思い検索するとイタリアは77% ∴日本はG7中この点でも最低)
●疲労回復におけるオフの重要性:心理的距離(psychological detachimennt)仕事のことを忘れているか、全く考えないか、距離を置けているか、負担から離れて一休みできているかで回答する指標があり、寝言で議会のことをよく語っている(笑)と言われる私はオンオフのメリハリがついていないということを再認識。
クーリングオフの重要性。職業人から家庭人に戻る時間が必要。(よく夫に疲れているんだからテレビ見るなよと言われますが、それは在宅自由時間の確保の一環なのか、とか。)そしてこの在宅自由時間をとることもなく、仕事で帰宅後玄関で倒れこむように寝ることは過労徴候で過労死に至ることもあるので注意。
休み方の6つの秘訣 ドラマモデルは講師の方ご自身の余暇の過ごし方の例がわかりやすかったです。

社会的な課題


つながらない権利、大事です。教員の時も生徒と接するのは大好きでしたが、お昼時間だけは生徒と離れていたいという思いがありました。今の学校現場ではそれはとてもかなわないのでしょうか。県庁でもお昼休みや就業時間後は電話をかけないようにと周知されていますが、どうしも聞かなければいけないことを問い合わせてしまったりして、そこは徹底しなければですね。これを社会的に広げていく取組が必要です。
そして次の表に描かれたことが政治の力でどこまで推進できるのか。

最後のQ&Aでは、法整備と実態の乖離を解消するための問いがあり、弁護士さんから法律を全部守られたら私たち仕事がなくなるという弁護士さんの言葉にウケつつ、監督行政も含めて法を執行するというところに注力する、産業医らと連携し、あきらかに過労だという数字を突き付けていく。家族版チェックリストを活用して数字でつきつけることが大切だと。これらの資料はこちらの過労死等防止調査研究センターHPから本人やご家族による過労のチェックリストがあります。ためしてみてください。
東芝デジタルソリューションズ株式会社の過労死再発防止の取組が素晴らしかったので巣が長すぎるので次のブログに。