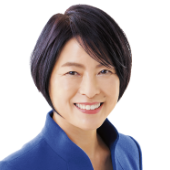予算委員会二日目 省エネ対策の効果的な普及について
井坂議員の写真を撮り忘れたので、予算委員会がおこなわれる本庁舎大会議場の写真を。ここに机と椅子が並べられ、一問一答でおこなわれます。
Q.地球温暖化対策を進める上で、対策の必要性を伝えるとともに一人一人がどのようなことができるのかを知ってもらうことが大切。今回の予算の中には、高校生・地域向け脱炭素普及啓発事業があるが、具体的な取り組みについて教えてほしい。(A.高校生と地域向け脱炭素ライフスタイルについて5つの高校を指定してワークショップを行っている)
Q.家庭用の省エネ対策として、省エネリフォーム助成制度があり、各家庭の断熱改修を支援している。2025年度の予算額と2024年度の実績を教えてほしい。(A.予算は600万円。24年度実績は300件の募集に対し350件の応募。補正予算を組んででもニーズにこたえるべきではと追求)

断熱改修ということであれば、学校での断熱改修の取り組みも必要だが、断熱化されている県立学校はどれくらいあるのか教えてほしい。(A.断熱改修は4校で終了。今後8校※で防水工事とともに実施予定(※数字は不確実なので調べます。)
Q.ここまで、断熱改修について伺ったが、高校生・地域向け脱炭素普及啓発事業は普及啓発事業としてグループワークなどを行っているとのことだが、啓発事業ということであれば、実際に体験をするような工夫した取り組みを行うことが重要ではないかと考えている。
私が注目したのは2023年に藤沢市で行われた市民と藤沢市が一緒になって行った断熱ワークショップの取り組み。この取り組みは、8組の親子が参加し、小学校の1教室の断熱改修を地域の工務店の人に手伝ってもらい、実施したもの。実際に教室の壁に断熱材を入れることや既存の窓に内窓を設置するなどの工事を大工さんと一緒に行い、改修前と改修後の室温を測定するもの。この取り組みは脱炭素チャレンジカップ2024環境大臣賞市民部門の金賞を受賞した。県としてもこのような体験を軸とした省エネの普及啓発事業を図る必要があると思うが、どう考えるか。(A.積極的な回答)
まだほとんどの学校で断熱改修がされていないとのことでしたので県立高校をフィールドとして、それこそ県立工業高校には建設科などもあり、授業の一環として行えば実践教育となり、また、地域住民と一緒になって学校を活用した断熱改修のワークショップなどを行うことでよりいっそう省エネの取り組みが広がることになる。そして、省エネ改修の普及にもつながるという相乗効果が期待できるのではないか。