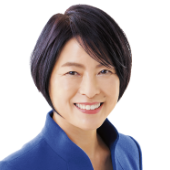県立中原支援学校(川崎市) 高等部卒業式に参加しました。
1974年(昭和49年)に肢体不自由教育の養護学校として開校、2003年(平成15年)に高等部知的障害教育部門が併設、2009年(平成21年)には県立住吉高校内に高等部知的障害教育部門分教室が設置されました。現在202名の児童生徒が在籍します。7台のスクールバスが児童生徒の通学を支えているとのことです。中原養護学校は近年名前を改め中原支援学校と呼ばれるようになりました。老朽化していた後者も回収されてすっかりきれいになりました。
みなさん、ご卒業おめでとうございます。小学部中学部は日程が合いませんでしたが高等部は雪の舞う3月19日に行われた卒業式に参加しました。これまでも何度か参加させていただきました。肢体不自由教育部門と知的障害教育部門の生徒さんたち、さらに住吉高校の分教室に通う子たちが本校の卒業式に参加しています。先生たちに車いすを押してもらい、中には状況を理解されているのかわからない子たちもいますが、多くの生徒がこの晴れの舞台をかみしめているのがわかります。
校長先生が一人一人におめでとうございますの言葉を掛けながらにっこり笑って賞状を手渡し、子どもたちはそれぞれのやり方で賞状を受け取る。みんなで一斉に保護者のみなさんにメッセージを送るシーンでは涙する保護者の方の姿。来賓の中には卒業生が就職する企業の方々も来られていました。子どもたちをよろしくお願いいたします。


PTAの方だったかのメッセージの中で「お弁当」の言葉があり、分教室の子たちには給食が出ないことを意識させられました。分教室といっても病院の中に設置されたりする本来の分教室の形ではなく、普通科の高校の空き教室を活用した形態です。神奈川県は全国でも例をみないほどの分教室の数が多く20校もあります。特別支援学校の数は29校。増え続ける知的障害の子たちを受け止めるキャパシティがなく、当初は時限措置として5年間で解消するとされたものがいつの間にか「新たな学びの場」と位置づけが変えられ、もう22年にもなります。通ってくる子たちは自分はどこの学校の所属なのか生徒も親も理解しにくいといいます。
施設の点でも処遇の点でも本校と格差があり、県議一期目は分教室で教える先生から一度見に来てほしいとお声掛けいただき、分教室をいくつか議員団で視察させていただき、分教室には高校の名前はあってもその敷地に特別支援学校の分教室があることもわからない、使える教室の数も少なく、家庭科室兼図書室県図工室みたいになっていること、高校の子どもたちの使わない時間を縫うようにグラウンドを「使わせていただいている」状況を改善しようと本当にしつこく追及しました。その後2校の特別支援学校の新設、1校の改築が決まり、分教室も5教室から1教室増やされ、校名板も設置されることになりました。職員室と保健室が兼用だった点については壁で仕切られることにもなりました。現場は先生たちも子どもたちも頑張っていて、例えばダンスで有名な分教室もあって、その分教室に憧れて入ってくる子たちもいるとか胸温まる話は聞こえてくるものの、特別支援学校の整備が追い付いていないこと、障がいのある子とない子が共に学ぶインクルーシブ教育の名で、教育資源が乏しいまま障がいのある子一人一人の成長が保障されているとはいいにくいインクルーシブ教育実践推進校の実態など神奈川の教育の大きな課題になっています。今、海老名市とともに進められようとしているフルインクルが理念倒れにならないためには国においても大幅な文教予算増が必要だと考えています。
話が脱線しましたが、この日の卒業式では住吉高校の校長先生も来られていて、中原支援学校本校と分教室で交流が持てている状況がうかがえました。私は遠慮なく「以前分教室の子が肩身狭く学んでいる実態をみたんですが」と住吉高校の校長先生に問うと、「それは物理的な問題として本当にあるのですが、高校が既得権益みたいになったらいけないのでそこはしっかり話し合いながら共に使っています」とのことでした。「高校と支援学校の両方の卒業式に出られて自分は得だなと思う。」と。
(以前分教室を有する高校の校長先生と話して「分教室の方の卒業式はいつでしょう」と何気なく聞いた際、「さあ」という返事が返ってきてとてもさみしい思いがしたものです。)
保護者の方々がどういう思いでここまで育て上げられたかと思うと感慨ひとしおです。同じく保護者の方のメッセージにそれがうかがえました。多くは企業への就職か作業所という新しい道を歩まれます。「体調の関係で式に出られない子はいましたが、全員無事卒業できました」と校長先生のお話。皆さんの未来に幸あれと願い、この日も胸アツでした。
そういえば、県立学校の校長室には文教常任委員会の委員の名簿が貼ってあります。私は今年度は文教常任委員ではないわけですが、あの掲示を見るたびに背筋が伸びる思いです。