小中一貫校を訪ねました。
 5月25日月曜日、霧が丘小中学校を視察させていただきました。畑野君枝衆議院議員と加藤リカ緑区市会候補と一緒です。訪問時に衣装の打ち合わせなどするはずもないのですが、偶然モノトーンな三人になりました。
5月25日月曜日、霧が丘小中学校を視察させていただきました。畑野君枝衆議院議員と加藤リカ緑区市会候補と一緒です。訪問時に衣装の打ち合わせなどするはずもないのですが、偶然モノトーンな三人になりました。
JR横浜線 十日市場駅からタクシーで緑に囲まれた霧が丘まで。息子のサッカーの試合で訪れたことがあったことを思い出しました。校長先生にお話しすると、広いグランドはよく試合会場として利用いされるのだということでした。
小中一貫校になって5年。当初は「一貫校である意味がわからない。地元としてどんな協力ができるのか」と地域からは疑問の声が出されていたということでした。しかし小学校から中学へ私立へ流れずほとんどの子が進学するということは学校への信頼があるのかな、また、大きな9年生が小さな1年生をいたわるように見守る画像からは思いやりの心の醸成という目的にはかなっているのかなという気もしました。
しかしいつでもどこでも打ち合わせが持てるよう校内各所に電話が取り付けられているという事実には、多忙化を促進しないかという畑野さんからも懸念が示されました。
私は県の緊急財政対策をうけた教育臨時調査会を傍聴したときに、中高一貫校を広げる方針の中で「校長が一人で済む。副教科の先生も一人で済む」という議論を聞いたことがあり、その発想に呆れたことがあります。この学校での人員配置はそういったことはないようで、そこは安心したものの、やはり先生方に試行錯誤を迫りながらのこの一貫校施策には疑問を感じざるを得ませんでした。
霧が丘では「無理なく焦らずゆっくりとできることから」これを合言葉に工夫をしておられます。先生たちの努力が報われ、子どもたちに無理のない形でこの試みが成功することがない限り、財政面の理由から無理に推進していく方針は疑問です。
畑野君枝さんが国会質問した内容をご紹介しておきます。
ちなみに、小学校から中学校に上がったて環境が激変した時のストレス(中一ギャップ)を解消するためにということを口実に小中一貫校は推進されています。しかしそういうギャップが人を成長させていくのではないでしょうか。小中一貫で慣れた環境ででは高1ギャップは?大学ギャップは?社会人ギャップは?

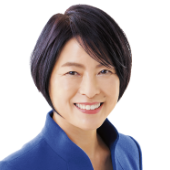


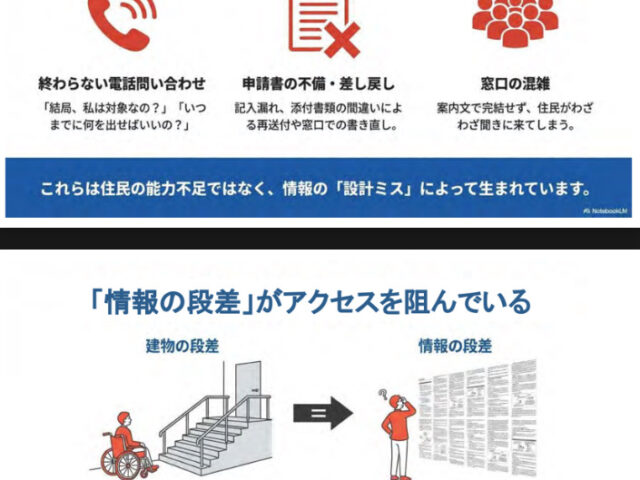



コメント
「小中一貫校」を制度化する学校教育法改定案が5月29日(金)、衆院文部科学委員会で可決されました。教育には門外漢の私でも一貫校施策には疑問を感じます。そして安倍内閣は全てが「拙速」いや「結論ありき」の国会運営に怒りを禁じ得ません。
私事ですが昨日(5月31日(日))「マイナンバー制度導入と危険性」なる学習会に参加しました。いわゆる現行の「マイナンバー法」(2015.10.5施行)ではマイナンバーの利用範囲は①社会保障、②税、③災害対策と限定されています。また「マイナンバー法」附則第6条で、「法律施行後3年をめどに内容を検討し、所要の措置を講ずることとされている。」(一部省略)と規定されているにもかかわらず、(法施行前)新たに①預金口座、②特定健診データ、③予防接種の履歴等に適用拡大を推進する「マイナンバー拡大法案」を5月21日(木)に衆議院で可決してしましました(現在、参議院内閣委員会にて審議中)。
このような国民生活に直結する法律すら無視するような暴挙や拙速な手法(すべてがこのような手法です。)に「戦争法案」含めて「NO!」の声を上げ続けなくてはならないと考えます。
私の経験(市立大曽根小から私立・桐蔭学園中・高(中学1年から高校2年まで現都筑区・すみれが丘に引越す、高3から大曽根(貸家にしていたところにもどる))。通学時間を約90分から約半分にするというものでした。(過度なプレッシャーをかけないため大曽根にすこし飽きたからと後で言われました・弁当を朝早くつくるのが大変(これは本音))。
私としては現状の6.3.3制よりも5.4.3制もしくは4.4.4制がベストかと思います。公立から私立男子校というギャップは大きかった。(私が高2から女子部・別学ができました)住むところを変えるのもかなりのストレスがかかり抽象的な思考に影響があると読んだことがあります。英語教育の現状に詳しく知りませんが、日本語、他教科のあと小4ぐらいから少しずつやればよいと思います。理系・文系分けのカギとなる数学では三角関数から脱落してしまいました。少しは参考にならないかと願い書いてみました。
25日、霧が丘にいらしていたのですね。地元は「防犯・防災・教育日本一」をスローガンに私は3時からのパトロール中でした。直前に地震があり、ヒヤッとした一日でした。現校長先生は2年目、今年やっと中学受験する児童が一桁になりました。昨年までは20人程(100人の内)いましたね。学区が霧が丘だけというのも、特別ではあります。一貫校を受ける時に、中学校給食の導入を条件に出しました。何でも一番を目指す地域で、小学生6年を富士山レーダー観測所に、又昨年より中学生をベトナム・カンボジアに自治会の補助を出して連れて行っています。
ギャップ、私もそう思います。
試行錯誤しながら、新しい環境に慣れていく能力も大切だと思います。
息子が通っている各学年一クラスしかない小学校のことを、
一クラスしかないのは”変化がなくて可哀想”と言われます。
義務教育を小学校と中学校に分けたのには、理由があるんじゃないですか?
理由が無ければ、最初から義務教育に9年かけたらいいと思いますが。
鈴木さん
全く何もかもが拙速ですね。
マイナンバーも、2年前からその危険性を訴えるべしとよく一般の人からいわれていました。本当に恐ろしい個人監視法です。
全力でこれも食い止めなければ。
佐藤さん
あら!霧が丘の地元でいらしたのですね。
中学校給食?霧が丘中学ではあるのですか?それはまったく想定していませんでした。おしえてください。
ベトナムでしたか、地元の町内会に連れて行ってもらえたのは地元に受け入れられたと感じていますと校長先生がおっしゃっていましたよ。
須藤さん
そうそう、いじめられていた子が中学校になって生まれ変わったという例もたくさん聞きますしね。
霧が丘は、もともと3小学校が統合され、霧が丘小学校になりました。その際にも、小中一貫校を受ける際にも、地域の条件として中学校給食を要望しました。勿論却下されましたが・・今は小学校の給食も民間委託です。地域としては、ほかはダメでも霧が丘中学校には給食を導入させたいと今も考えています。一番が大好きですから・・・